窓の安全面とは?
安全な窓とはどんな窓でしょうか。
安全の反対は危険。
窓は開閉を行うので、いろいろな面で安全性を考えないといけません。
私が間取りを設計している間、窓の安全など考えたことはほとんどありませんでした。
でも、宿泊体験や展示場に家族で行った時に、いろいろと感じたことを反映しました。
そして実際に家が建って、そして住んでみると、いろいろと見えてきます。。。
住んでみないとわからないことも多いものです。
窓の安全面で考えるには以下ような点があります。
窓の基本的な開閉での安全面
不可抗力による窓の危険性
窓ガラスの危険性
設置場所による窓の危険性
順にみていきましょう。
窓の基本的な開閉での安全面
窓には、開き戸と引き戸がありますが、それぞれに構造が異なります。
昔ながらの家のほとんどは引き戸です。
私も引き戸の家に住んでいました。
開き戸は、玄関と勝手口しかありませんでした。
引き戸の場合には、引いた窓で手を挟むということがありますが、そのような経験はほとんどありません。
しかし、開き戸の場合には、窓の縁で手を挟んでしまう危険性は高いと思います。
慣れていないだけではないと思いますが、引き戸には2つの危険があります。
1つは窓と窓枠との間
そしてもう1つは、それをロックする装置の部分です。

やはり駆動部分が多いと危険が高くなります。
主に指を挟む可能性があります。
大人であれば大丈夫ですが、子どもの場合に、とても危険がことが何回かありました。
不可抗力による窓の危険性
不可抗力というのはどういう時に起こるでしょうか。
窓は外とを遮断するためにあるので、外部の天気などの影響を受けます。
特にあるのは、風です。。
引き戸の場合にはガタガタするだけですが、開き戸の場合には、風で窓が閉まってしまうことがあります。

開き戸のほとんどは、半開状態でつかうことが多いと思います。
雨が降っていなくとも、春や台風後などで風が強い時などの場合、窓が風で閉まってしまうことがあります。
これがとても危険です。
窓を操作している時にはとても危険です。
強制的に締まってしまうので、手を挟むことがあります。
窓の半開状態が固定できないのが問題のようにも思いますが、、、、
子ども部屋などではとても心配になります。
窓ガラスの危険性
窓ガラスは、やっぱりガラスなので割れることがあります。
いまどきのガラスは、割れても飛び散らない仕様になっているということですが、それでも、地震でぶつけたり、家具の移動でぶつけてしまうこともあるでしょう。
竜巻も各地で起こっているので、外部から瓦が飛んで来たなんてことも可能性としてはありますね。
可能性だけを見るととても危険ではありますが、最新の窓ガラスを選んでおけばある程度は防げます。
また吹抜をつくった場合にも、窓が割れて落下する可能性についても考慮しておく必要があります。
特に、吹抜に電球をつり下げている場合などは、その電球が大きく揺れて窓ガラスに当たることもあります。
展示場などで吹抜の上を眺めて、
この吹抜で地震が起こったらどうなるのか?
ということを考えて見ることも大切ですね。
設置場所による窓の危険性
わが家では、子ども部屋の窓はすべて引き戸にしました。

やはり、開き戸を全開にすると、大人でも怖いのです。
この体験は、ぜひ、展示場でやってみることをオススメします。
しかも、2階の窓で、腰窓の大きめもののが良いでしょう。
窓を開けると、そのまま落ちていきそうです・・・・
これ、絶対にうちの子・・・落ちるよ・・・・
そんなことを察し、すべて引き戸にしました。
引き戸では落ちないし・・・・
そして住んでみて、わが家の寝室で危険がことがありました。
腰窓は子どもがステップで簡単に登れてしまいます。
特に、一条工務店のi-smartの窓は、外壁との厚みがあるので、そこが15㎝程度のカウンター状態になります。
子どもは簡単にそこに登れてしまうのです。
そして、全開/半開のスイッチなど、子どもにとってはおもちゃです。
開き戸の全開状態

開き戸の半開状態

そして全開にスイッチを移動し、窓を開けてしまったわけです。

絶対に落ちますよね。。。
幸いにも、この手摺りに登っている状態で食い止めましたが、2歳の子にとっては何で怒られたのかわらかず。
子ども部屋は引き戸にしておいて良かった
当初は開き戸にしていました。
見た目にも、オシャレ感でも・・・
でも、引き戸で良かったです。
5歳と2歳の子が、落ちことを祈ります。。。
その他、安全面で考慮すること
開き戸でも高くすれば転倒は防げる
開き戸であっても、高さを調整すればある程度は防げると思います。
顔付近の高さまであれば、さすがに登らないでしょう。。。
それに窓も小さくなるので、風で強制的に閉じたとしても、さほど力がかからないはずです。
窓は安全に使いたい
窓がどのような危険性を持つのか、それは使ってみないとわかりません。
日頃から使ってきた家でどのような窓に触れてきたかという「慣れ」もあるでしょうが、ゲストや子どもなどにはその慣れはありません。
ゲストで泊まりに来た人でも、窓の開閉はするでしょう。
そういうことも含めて、窓の安全性を考慮しておくことは大切だと思います。
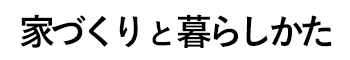



気になるキーワード